2025.04.14
建築基準法 その2 非常用発電機を設置する際に必要な建築基準法の基礎知識【技術解説版】
最終更新日:2025.07.04
- 知識
- 法律
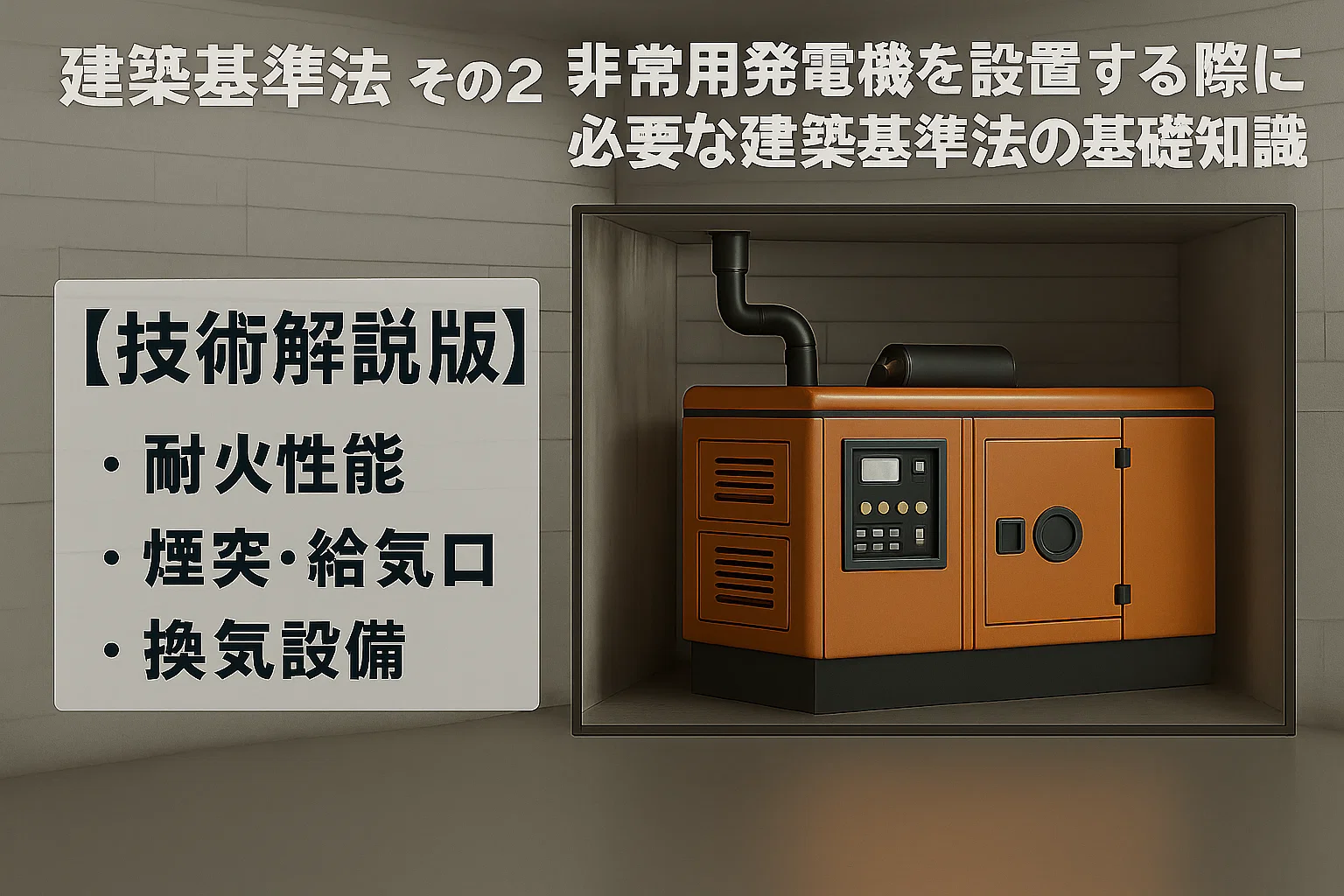
非常用発電機を設置する際に必要な建築基準法の基礎知識【技術解説版】
非常用発電機は、災害時にビル・病院・工場などの重要設備をバックアップするために不可欠な設備です。
その設置においては、建築基準法、消防法、電気事業法などの法令が複雑に絡み合います。
本稿では、特に建築基準法の観点から、発電機設置時に押さえるべき構造・区画・設備基準について技術的に詳しく解説します。
1. 建築基準法が関連する主な条文と観点
- 第20条(構造耐力):重量物設置による構造安全性の確保
- 第35条(特殊建築物等):避難・消火設備設置義務 (詳細基準は施行令126条の2〜5に委任)
- 第36条(安全上・防火上の技術基準):建築設備・採光・防火壁などを包括
- 施行令第112条の2〜(防火区画):室内区画の耐火構造・開口部防火設備
- 施行令第129条の3〜129条の15:非常用昇降機・非常用電源など機械設備の技術基準
非常用発電機は 1 台あたり1 t〜3 t 以上の重量があるため、 設置場所の床は十分な積載荷重(例:500〜1 000 kg/m² 〈約 4.9〜9.8 kN/m²〉)を満たしている必要があります。
屋上設置では構造計算書と照らし合わせ、 架台や基礎が局部荷重(点荷重)に耐えられる設計が求められます。
3. 振動・騒音対策と防振構造
発電機は稼働時に回転振動を生じるため、建築構造への振動伝播を防ぐために次のような対策が必要です:
- 一次防振:エンジン直下に防振ゴムやスプリング
- 二次防振:架台と建物構造の間に防振材を追加
- 架台設計:振動共振周波数を避けた寸法・剛性の確保(架台固有振動数 ≠ スラブ固有振動数)
- 耐震固定:施行令129条の15・国交省告示1388号に基づくアンカーボルト等で機器を固定
4. 換気・排気の設計基準
燃焼エンジンを使用する非常用発電機では、吸気・排気量の設計が重要です。
- 燃焼用吸気量:0.1〜0.3 m³/min·kW
- 冷却用換気量:4.8〜7.2 m³/min·kW (外気温差 ΔT10〜15℃ 想定)
- 合計目安:≈5〜8 m³/min·kW
- 排気温度:400〜600 ℃ → 耐熱・断熱ダクトが必要
- 排気位置:建物開口部や避難経路から 3 m 以上離隔(不燃外壁+防火戸を設置する場合は短縮可)
- 風下への巻き込み:防風板・偏向板・風洞解析などで設計
5. メンテナンス空間と搬出入ルート
発電機設置には、点検・修理・機器交換が可能な空間を確保する必要があります。
- 周囲 600 mm 以上(メーカー推奨:前面 800 mm、側面 500 mm 以上)
- 天井高さ:搬出・吊り上げに十分な余裕(例:2.5 m 以上)
- 搬出入ルート:扉幅 900 mm 以上、階段やリフトも確認
- 定期点検:消防法に基づき、6 か月ごとの機器点検と年次総合点検が義務
6. 防火区画との関係と防火措置
発電機室が防火区画に該当する場合、以下のような耐火措置が求められます:
- 壁・天井:耐火構造(例:RC 壁100 mm=1 時間 / 120 mm=1.5 時間 / 150 mm=2 時間 等)、防火被覆併用可。
厚さは区画位置・要求等級により決定。 - 出入口:防火扉(自閉装置付)、火災時に自動閉鎖されるシャッター
- ケーブル・配管:防火区画貫通部に認定シーリング材で防火措置
これらは消防法とも重複するため、建築確認申請時の図面と整合性を取ることが重要です。
まとめ|法令遵守と技術的整合が設備稼働の要
非常用発電機の設置は、構造設計・建築設備・防火計画と密接に関係し、建築基準法の正確な理解と反映が不可欠です。
施工前の計画段階で、建築士・構造設計者・設備設計者・施工管理者が連携し、設置条件と法的要件の整合性をとることで、安全・確実・長寿命な設備導入が可能となります。
◎便利なツール・発電機サイト
- 発電機負荷計算ツール – 負荷を計算し、必要な発電機容量を検討できます。
- ケーブル選定ツール – 発電機からの配線を安全に行うためにケーブルサイズを確認可能。
- 発電機.jp – 各種発電機の導入事例や導入検討のポイントを網羅。移動式大容量発電機の情報もチェックできます。