コラム②:自家発電設備の大気汚染防止法による排出規制 (排出基準の具体例)~ばい煙発生施設を中心に~
- 知識
- 法律
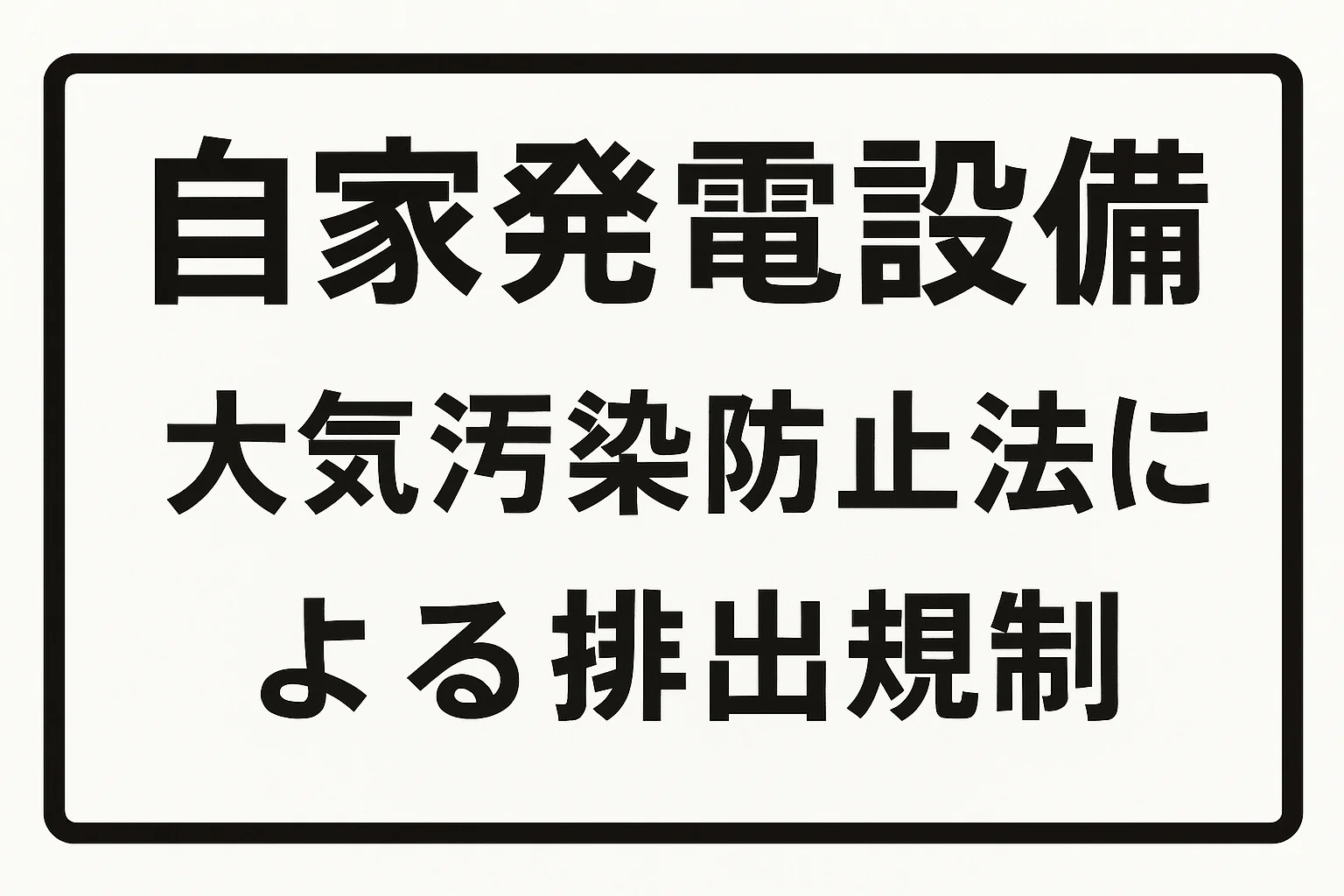
コラム②:自家発電設備の大気汚染防止法による排出規制(その2)
~ ばい煙発生施設を中心に ~
(本稿の法令・情報は 2025年8月20日 現在)
自家発電設備は停電時のバックアップやBCP(事業継続計画)、ピークカットなど、さまざまな用途で利用されます。しかし、燃料を燃焼して動力を得る都合上、一定規模を超えると「ばい煙発生施設」に該当し、大気汚染防止法(以下「大防法」)による排出基準を遵守する必要があります。本稿では、同法における排出基準の具体例を中心に、自家発電設備がどのように規制されるのかを解説します。
1. 自家発電設備が「ばい煙発生施設」に該当する条件
大防法施行令 別表第1により、以下の燃料の燃焼能力(重油換算)を超える自家発電設備は「ばい煙発生施設」に該当します(別表:施行令)。
- ガスタービン・ディーゼル機関:50 L/h 以上
- ガス機関・ガソリン機関:35 L/h 以上
手続:大防法では届出(原則60日前)が基本です(設置・変更ほか)。詳細は環境省の案内「ばい煙発生施設の設置の届出」をご参照ください。
なお、自治体条例で上乗せの許可・届出が課される地域もあります(例:東京都の上乗せ基準、横浜市の手続き解説)。
2. 規制される「ばい煙」の範囲
大防法の「ばい煙」は次の3区分で規制されます(定義・枠組みの概説は環境省解説)。
- いおう酸化物(SOx)
- ばいじん
- 有害物質(政令で定める物質)…
①カドミウム及びその化合物、②塩素・塩化水素、③フッ素・フッ化水素・フッ化珪素、④鉛及びその化合物、⑤窒素酸化物(NOx)
3. いおう酸化物(SOx)の排出基準 ― K値規制
3-1. K値規制の式と考え方
SOxの許容排出量は、排出口の高さ(有効煙突高)に応じて次式で定まります:
q = K × 10-3 × He2
q:許容排出量(m3N/h)、K:地域別定数、He:補正された排出口の高さ=煙突実高+煙上昇高(出典:環境省・東京都)
3-2. 地域ごとのK値(一般/特別)
- 一般排出基準:K=3.0~17.5(16段階)
- 特別排出基準:K=1.17~2.34(汚染が著しい等の地域で新設に適用)
全国は121区域に区分され、区域番号ごとにK値が決まっています。例:
・札幌市(区域一部除く)K=4.0/東京都特別区 K=3.0(第33号)/大阪市 K=3.0(第58号)/福岡市 K=8.76(第89号)
(参考:内発協ニュース 2019年10月号)
3-3. 計算手順(数値例)
- 区域とK値:例として「東京都特別区」を仮定し K=3.0。
- 有効煙突高 He:煙突実高 25 m、煙上昇高 5 m → He = 30 m。
- 式に代入:q = K × 10-3 × He2
q = 3.0 × 10-3 × (30)2 = 3.0 × 10-3 × 900 = 2.7 m³N/h
※同じHeでもKが小さい区域ほど許容排出量qは小さく(=厳しく)なります。区域・K値は必ず所轄資料で確認してください。
4. ばいじんの排出基準(濃度規制)
ばいじんは排出ガス中の濃度(g/m3N)で規制され、標準酸素濃度補正の考え方が採用されています(一般式の解説:環境省)。
| 機関種類 | 標準O2濃度 (On) | 一般基準 (g/m³N) | 特別基準 (g/m³N) |
|---|---|---|---|
| ガスタービン | 16% | 0.05 | 0.04 |
| ディーゼル機関 | 13% | 0.10 | 0.08 |
| ガス機関 | 0% | 0.05 | 0.04 |
| ガソリン機関 | 0% | 0.05 | 0.04 |
※内燃機関類については当分の間、On=Os(酸素補正なし)とする運用注記があります(出典:環境省「ばいじん・NOx基準一覧」)。
4-2. 判定単位と測定頻度の整理
- 判定単位:原則として排出口(ばい煙発生施設)ごとに、基準状態(0℃・1気圧、乾きガス)で判定します。
- 酸素補正:一覧の標準O2(On)に基づいて補正します。内燃機関類は当分の間 On=Os(補正なし)の運用注記があります。
- 測定頻度:施設種別・規模により施行規則・自治体要領で定められています(例:定期測定、記録・保存)。
※非常用施設の扱いは次章参照。
5. 窒素酸化物(NOx)の排出基準(濃度規制)
代表的な基準値(燃料の燃焼能力が該当規模を超える場合)を示します。詳細は環境省の一覧を参照してください(同一覧ページ)。
| 機関種類 | NOx基準(ppm) | 標準O2濃度 (On) |
|---|---|---|
| ガスタービン(50 L/h以上) | 70 | 16% |
| ディーゼル機関(シリンダ内径400mm未満) | 950 | 13% |
| ディーゼル機関(シリンダ内径400mm以上) | 1200 | 13% |
| ガス機関(35 L/h以上) | 600 | 0% |
| ガソリン機関 | 600 | 0% |
※本表のOn値は基準設定時の参照値ですが、当分の間はOn=Os(酸素補正なし)の注記が付されています。
5-3. 非常用発電設備(非常用施設)の特例
施行令別表第1の29~32項に該当する原動機のうち、専ら非常時に用いるもの(非常用施設)は、当分の間、大防法によるばい煙の排出基準の適用外(定期測定も適用外扱い)とされています。適用可否は設置形態・運用実態で判断されるため、必ず所轄で確認してください。
付録:ケーススタディ(400kVA級ディーゼル想定)
参考電流(3相3線):200V時 ≒ 1,155 A、400V時 ≒ 577 A(S=√3VI より)。
- 対象の確認:ディーゼル機関で燃焼能力が50 L/h以上(重油換算)なら「ばい煙発生施設」。
- SOx(K値):区域のKと有効煙突高Heから許容排出量qを算定(例:3-3参照)。
- ばいじん:基準0.10 g/m³N(特別:0.08)、標準O2=13%(当分の間 On=Os)。
- NOx:シリンダ内径で規制が分かれる(<400mm:950 ppm、≧400mm:1200 ppm、標準O2=13%〔当分の間 On=Os〕)。
- 重油/熱量換算:仕様書の燃料消費や低位発熱量から重油換算・GJ/h換算を行い、閾値判定と届出要否を確認。
- 実務:メーカー排ガスデータの標準状態・O2条件を確認、必要に応じ消音器・触媒・尿素SCR等の対策を検討。条例の上乗せや特別基準の有無は所轄に事前相談。
6. まとめと留意点
- 燃焼能力がGT/ディーゼル50 L/h以上、ガス/ガソリン35 L/h以上なら、ばい煙発生施設として大防法の排出基準が適用。
- SOxはK値規制(q=K×10-3×He2)、ばいじん・NOxは濃度規制。地域の特別排出基準や条例の上乗せに注意。
- 内燃機関類は当分の間、酸素補正なし(On=Os)の運用注記あり(計算時に要確認)。
- 実務は所轄への事前相談と、最新の法令・条例・運用通知の確認が安心です。
7. 注意事項
本コラムは大防法の概要解説です。実際の運用・法改正・各自治体条例により規制内容は変動し得るため、必ず最新情報を所轄行政機関にご確認ください。個別案件や不明点がある場合は、専門家にご相談ください。
参考リンク(一次情報・公的資料中心)
- 大気汚染防止法(e-Gov):法本文
- 大気汚染防止法施行令(e-Gov):別表第1(29~32項 ほか)
- 工場・事業場の規制方式(環境省):K値の範囲(一般/特別)
- SOx(K値)解説:環境省/東京都
- ばいじん規制(補正式の解説):環境省
- ばいじん・NOx基準一覧(内燃機関の数値・注記):環境省
- 区域とK値の具体例(121区域の解説・事例):内発協ニュース 2019年10月号
- 届出の手引き:環境省ワンストップページ
- 条例の上乗せ例:東京都/横浜市
- 重油換算・発熱量換算の考え方(公的資料):所轄自治体の手引き・環境省通知等をご確認ください
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。
\ 発電機.jpからのおしらせ/
発電機レンタル・購入は 発電機.jp におまかせ!
国内トップクラス 2,800台超 の保有から、
現場にピッタリの機種をスピード手配します。
便利な無料ツールもご用意しています。お気軽にご利用ください!
📩 発電機.jp WEBからのご相談・お見積りはこちら
「どの発電機を選べばよいか分からない」「ケーブルも一緒に手配したい」など、専任スタッフが用途にあわせてご提案いたします。
※お急ぎの場合も、まずはフォームからご連絡ください。担当者より折り返しご案内いたします。