コラム①:自家発電設備の環境規制(基本解説)~ 大気汚染防止法の基礎とばい煙発生施設の概要 ~
- 知識
- 法律
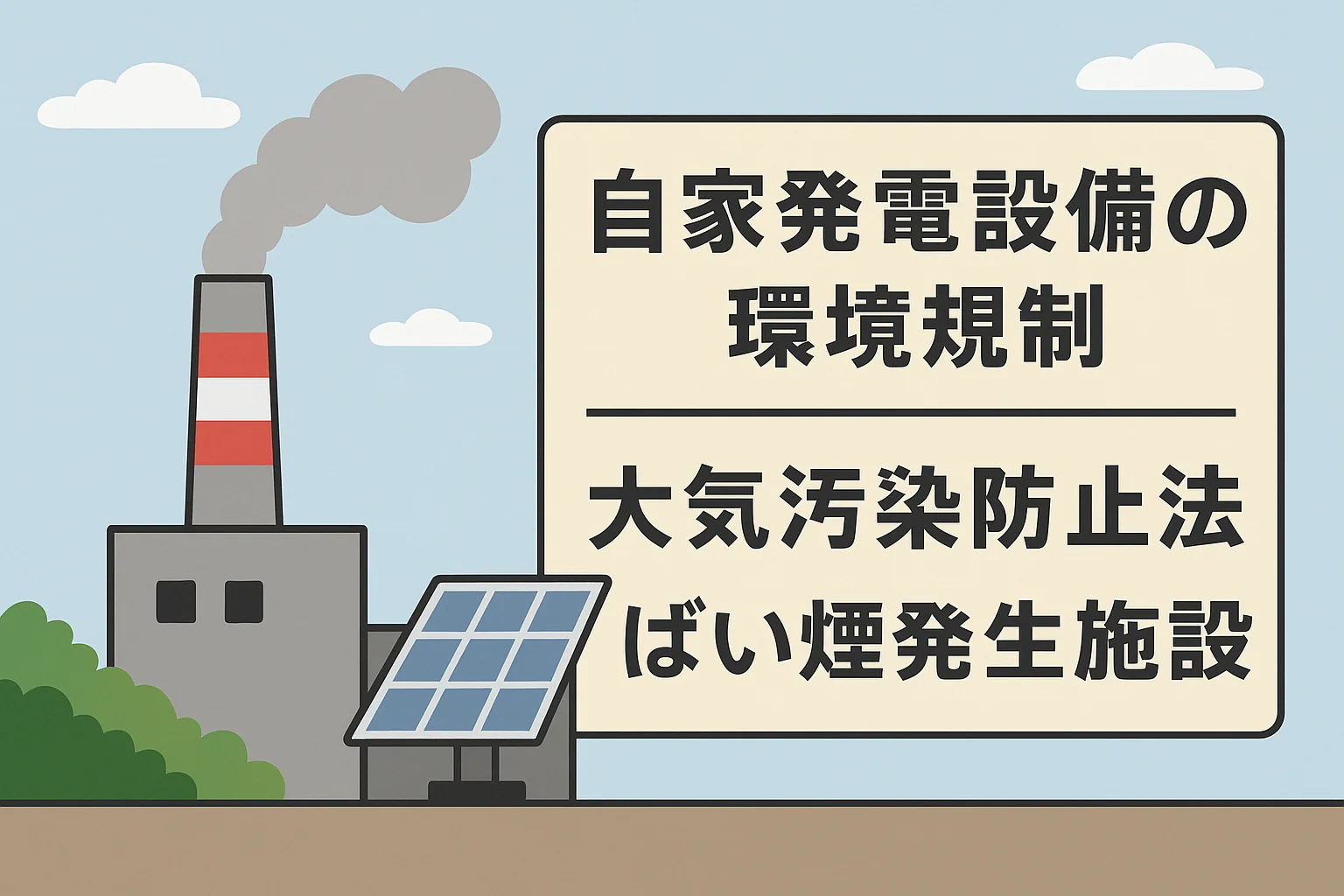
コラム①:自家発電設備の環境規制(その1)
~ 大気汚染防止法の基礎とばい煙発生施設の概要 ~
(本稿の法令・情報は 2025年8月20日 現在)
1. はじめに
自家発電設備は非常用電源やピークカットなどで広く利用されますが、環境規制への適切な対応も重要です。大気汚染防止法(以下「大防法」)は、「ばい煙」の排出規制を通じて大気環境の保全を図る法律です。本コラムでは、ばい煙の定義や「ばい煙発生施設」の範囲など、基本ポイントをコンパクトに整理します。
2. 大気汚染防止法で規制される「ばい煙」とは
大防法第2条により、「ばい煙」は次の物質を指します(定義条文:法第2条)。
- 硫黄酸化物(SOx)
- ばいじん(いわゆるスス)
- 有害物質(政令で定める物質)…
政令で定める物質は ①カドミウム及びその化合物、②塩素・塩化水素、③フッ素・フッ化水素・フッ化珪素、④鉛及びその化合物、⑤窒素酸化物(NOx) です(環境省「ばい煙の排出規制」)。
これらの物質を多量に排出する施設には、環境基準の維持・達成のため、施設・規模に応じた排出基準が適用されます(概説:環境省「工場及び事業場からの規制方式」)。
3. ばい煙発生施設とは
大防法第2条第2項は、ばい煙発生施設を「工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生・排出するもののうち、政令で定めるもの」と定義します(法第2条第2項)。具体の種類・規模は 施行令 別表第1(「8の2」を含む33種類)に列挙されています(一覧:環境省「対象となるばい煙発生施設」)。
留意点:自家発電設備は通常「固定発生源」に該当します。移動用の発電設備であっても、工場・事業場に設置して継続使用する実態があれば、届出等の対象(固定発生源)となる場合があります。具体の判断は所轄へご確認ください。
4. 自家発電設備も「ばい煙発生施設」になる?
発電設備に関連する別表第1の該当項目と規模要件(重油換算 L/h)は次のとおりです(根拠:施行令・別表、自治体資料例:柏市、古河市)。
| No. | 対象となる施設 | 適用規模(重油換算 L/h) |
|---|---|---|
| 29 | ガスタービン | 50 L/h 以上 |
| 30 | ディーゼル機関 | 50 L/h 以上 |
| 31 | ガス機関 | 35 L/h 以上 |
| 32 | ガソリン機関 | 35 L/h 以上 |
※「重油換算」の取扱い(例:液体燃料10L=重油10L、気体燃料16m3=重油10L 等)は、環境省通知等で示されています(例:「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について」の重油換算取扱い参照)。
したがって、上記規模以上の自家発電設備は「ばい煙発生施設」として大防法の排出規制の対象となります。
5. ばい煙発生施設としての主な義務
① 排出基準の遵守
SOx・ばいじん・NOx 等の排出について、施設種別・規模に応じた基準に適合させます(概説:環境省まとめ)。
② 設置・構造等の変更時の届出
ばい煙発生施設を新設・変更・廃止する場合は、所轄(都道府県等)への事前届出が原則必要です。
【電気工作物の手続特例(法第27条)】
発電設備が「電気事業法の工事計画届等の対象となる電気工作物」に該当する場合、大防法側の届出は手続上の適用除外となり、電気事業法の工事計画手続において提出する公害防止関係資料が、所轄自治体へ通知される仕組みです(根拠:法第27条、通知例:経産省・公害防止関係資料の都道府県等への通知)。
③ ばい煙量・濃度の測定・記録・保存
大防法・施行規則に基づき、施設種別・規模に応じた頻度で測定を行い、測定結果を記録して3年間保存します(施行規則:記録・保存義務、自治体解説例:東京都・ばい煙の測定)。
④ 違反時の措置
改善命令・使用制限等の行政措置や、記録義務違反等に対する罰則が定められています(法令本体参照)。
【非常用発電設備の特例】
施行令別表第1の29〜32項に該当する原動機のうち、「専ら非常時において用いられるもの(非常用施設)」は、当分の間、大防法によるばい煙の排出基準の適用外(測定義務も適用外扱い)とする取扱いが、附則・通知等で示されています。もっとも、適用の可否や運用は設備の設置形態・運用実態で判断されるため、必ず所轄にご確認ください。
参考:環境省通知(環大規第237号)、業界Q&A(内発協・自家発電設備の環境規制(その2))、自治体資料例(福岡市 概要資料、埼玉県 資料)。
6. まとめ
- 大防法の「ばい煙」は、SOx・ばいじん・政令で定める有害物質(NOx 等)を含む概念です。
- 自家発電設備のうち、ガスタービン・ディーゼル機関は 50 L/h 以上、ガス機関・ガソリン機関は 35 L/h 以上(いずれも重油換算)で「ばい煙発生施設」に該当します。
- 届出・排出基準の遵守・測定記録の3年間保存が基本。電気工作物は法27条の手続特例により、電気事業法の工事計画手続で公害防止関係資料が所轄へ通知されます。
- 非常用発電設備(非常用施設)は、当分の間、排出基準(および定期測定)の適用外扱い。適用可否は個別確認が必要です。
7. 次回コラムのご案内
次回のコラム②:自家発電設備の大気汚染防止法による排出規制(排出基準の具体例)では、以下の点をわかりやすく解説します。
- SOxのK値規制の考え方と計算手順(地域区分・排出量からのK値算定)
- ばいじん・NOxの濃度規制(判定単位・測定頻度の整理)
- 重油換算・熱量換算の実務ポイント(換算表の読み方)
- 非常用発電設備の取扱い(当分の間の適用外と留意点)
- ケーススタディ:ディーゼル発電機(400kVA級想定)の適用例
8. 注意事項
本コラムは大防法の概要解説です。実際の運用・法改正・各自治体条例により規制内容は変動し得るため、必ず最新情報を所轄行政機関にご確認ください。個別案件や不明点がある場合は、専門家にご相談ください。
参考リンク(一次情報・公的資料中心)
- 大気汚染防止法(e-Gov):法本文(第2条・第27条 ほか)
- 大気汚染防止法施行令(e-Gov):別表第1(29~32項 ほか)
- 対象となるばい煙発生施設(環境省):一覧(33種類、8の2含む)
- ばい煙の排出規制(環境省・定義と基準の枠組み):解説ページ
- 測定・記録・保存(3年)の根拠:施行規則/自治体ガイド例:東京都
- 電気工作物の手続特例(法27条)運用:経産省通知(公害防止関係資料の都道府県等への通知)
- 非常用施設の「当分の間」取扱い:環大規第237号(非常用施設の届出等)/内発協Q&A/自治体例:福岡市, 埼玉県
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。
\ 発電機.jpからのおしらせ/
発電機レンタル・購入は 発電機.jp におまかせ!
国内トップクラス 2,800台超 の保有から、
現場にピッタリの機種をスピード手配します。
便利な無料ツールもご用意しています。お気軽にご利用ください!
📩 発電機.jp WEBからのご相談・お見積りはこちら
「どの発電機を選べばよいか分からない」「ケーブルも一緒に手配したい」など、専任スタッフが用途にあわせてご提案いたします。
※お急ぎの場合も、まずはフォームからご連絡ください。担当者より折り返しご案内いたします。