仮設現場でも必要!10kW以上の可搬型発電機と法令手続き【2025年8月】
- 知識
- 法律
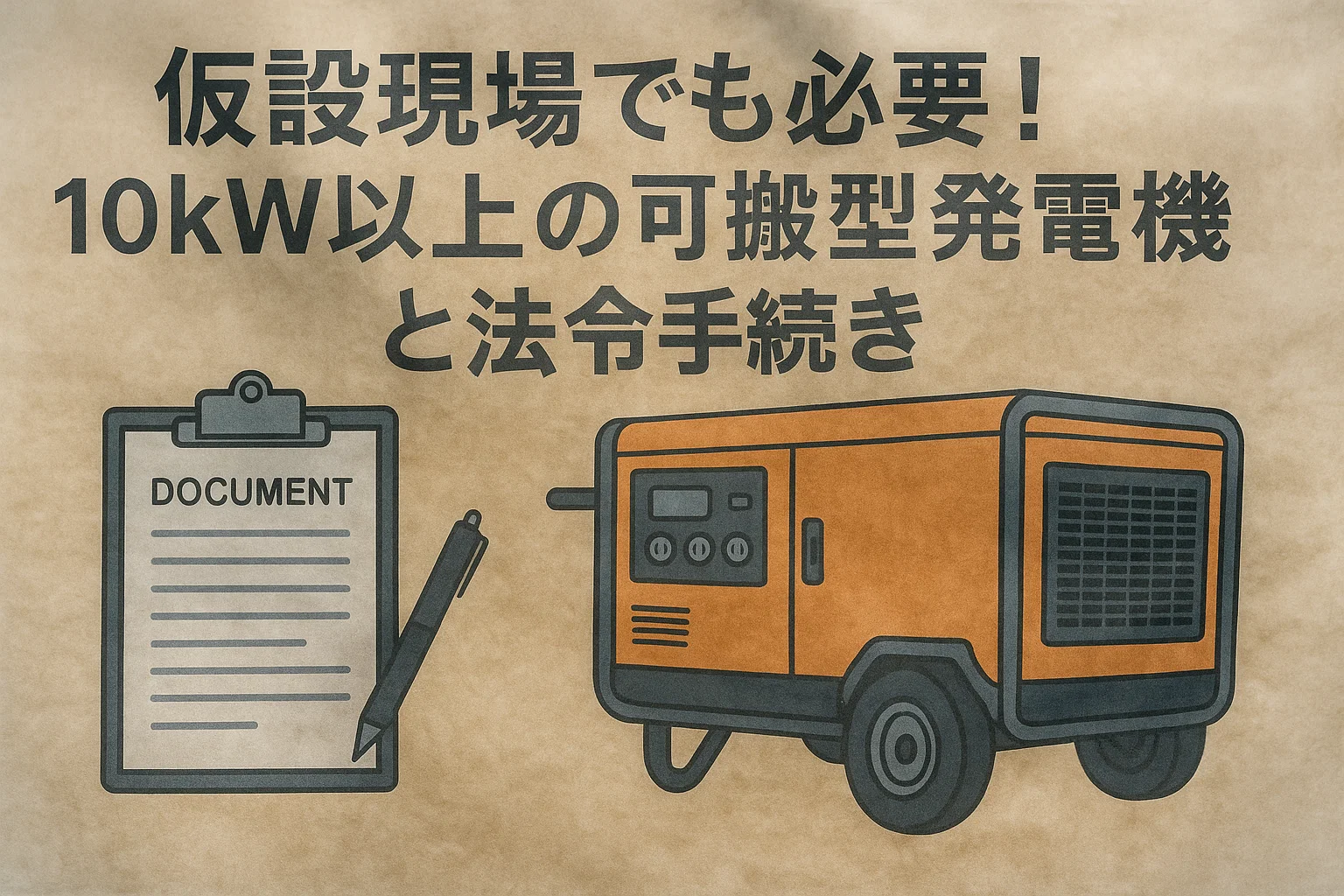
仮設現場でも必要!10 kW以上の可搬型発電機と最新法令手続き【2025年8月改訂】
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。(最終確認日:2025-08-20)
✅ 災害・緊急時が起きる前に「発電機レンタルの優先供給」の打ち合わせをしませんか?
災害や停電などの緊急時は、発電機だけでなくケーブル/分電/燃料を含めて手配が重なりやすく、必要なタイミングで確保できるかが課題になりがちです。
日本全国対応(離島・一部地域は条件が異なる場合があります)。平時のうちに、想定シーン・必要容量・設置条件を整理して、供給体制を一緒に作っておくと安心です。
※フォーム冒頭に「優先供給」または「緊急/災害」と記載し、現場エリア(市区町村まで)・想定稼働時間・機器名(分かる範囲で)を添えてください。
仮設事務所や建設現場、イベント会場など、さまざまな場所で活躍する可搬型発電機。特に12.5 kVA~49 kVAクラスは、空調や仮設照明、200A~400Aの溶接機などにも幅広く使われています。
「仮設だから届出や資格は不要なのでは?」と現場から相談を受けますが、
実は仮設・短期使用でも法令上の手続きや資格が必要です。
(2024~2025年の最新運用・電子申請の標準化も反映済み)
「仮設や短期利用なら手続きは不要」と思われがちですが、
出力10 kWを超える可搬型発電機は、仮設・常設を問わず 主任技術者の選任(電気事業法第43条)と保安規程の作成・届出(同法第42条、施行規則第50条)が必須です。
また、配線や燃料タンクの条件によっては消防法の届出や、電気工事士/認定電気工事従事者資格も必要となります。
※行政のデジタル化により、保安ネット(電気保安ネット)での電子届出が標準的な申請方法になっています。
なお、仮設向けには「移動用保安規程モデル」や外部委託(電気管理技術者等)による簡素化オプションが用意されていますが、これは免除ではなく“手続きの簡素化”です。
本コラムでは、現場でよく使われる可搬型発電機の手続きポイントを最新の法令と運用に基づいて、わかりやすく解説します。
10 kW以上は「自家用電気工作物」扱いに
定格出力が有効電力10 kW(おおむね12.5 kVA相当)を超える可搬型発電機は、自家用電気工作物として扱われ、次が必要になります。
※主任技術者の選任・解任時は、概ね30日以内に所轄へ届出が必要です(所轄:産業保安監督部)。
「仮設」でも免除はないが、手続きの“簡素化”は活用できる
「仮設・短期使用なら不要では?」という誤解が多いですが、10 kW超であれば常設・仮設を問わず選任と保安規程届出が必要です。
併せて、移動用保安規程モデルや、外部委託承認制度(電気管理技術者・電気保安法人)を活用することで、巡回点検等により運用を簡素化できます。
電子申請は保安ネットで行うのが標準です(各監督部の手続ページでも電子申請が標準と案内)。
工事計画・環境系の事前届出はどのケースで必要?
- 電気事業法の工事計画届(第48条):
高圧受電(受電電圧1万V以上~10万V未満)の需要設備等で対象。着工30日前までの届出が要件です。
12.5~49 kVA級の可搬機単体では通常対象外ですが、受電設備の構成により変わるため所轄に事前確認を。
参考:近畿監督部|工事計画届出/JEEA解説 - 大気汚染防止法の届出(ばい煙発生施設):
固定設置が前提。発電機は1機関あたりの燃料消費量で判定し、ディーゼル・ガスタービン=50 L/h以上、ガス・ガソリン=35 L/h以上で対象(中国四国監督部)。
移動式は原則対象外ですが、長期定置等の運用実態により固定扱いとなる場合があります(目安「同一場所で約3か月以上」など、自治体運用あり)。
なお非常用については排出基準の適用除外の扱いがありますが、届出や要否判断は所轄の環境部局へ必ず確認してください。
電気工事士・「認定電気工事従事者」にも注意!
- 自家用電気工作物の工事一般は原則「第一種電気工事士」の従事範囲です。
- ただし自家用の低圧部分(600V以下)の簡易電気工事は、第二種+「認定電気工事従事者」で施工可能(電気工事士法第3条4項)(電線路に係るものは除く)。
- 軽微な工事(端子へのねじ止め等)は資格不要の例外があります(電気工事士法施行令第1条)。
- 高圧受電や保護協調を伴う複雑な並列運転構成などは、第一種の実務範囲で対応するのが安全・確実です。
参考:電気工事士等の従事範囲/認定電気工事従事者(講習)/資格不要の軽微な工事
消防法(燃料タンク・携行缶)の届出と基準
- 指定数量(例):ガソリン=200 L、軽油・灯油=1,000 L(第4類危険物)。
合計が指定数量の1/5以上(ガソリン40 L~、軽油/灯油200 L~)は「少量危険物」として条例に基づく届出が必要。指定数量以上は設置許可が必要。 - 仮設現場でもタンクの容量・設置形態によって手続が変わるため、計画段階で所轄消防署に事前照会してください。
- 近年の改正・通知により、各自治体の様式や運用が更新されています。最新様式を必ず確認しましょう。
まとめ|仮設現場も法令遵守が大切
仮設現場でも「免除」される手続きは基本的にありません。ただし、移動用保安規程モデルや外部委託、保安ネットによる電子申請を活用すれば、準備工数や運用を大きく簡素化できます。
現場ごとに「出力・燃料・配線・受電方式・設置期間・タンク容量」を整理し、不明点は必ず所轄(産業保安監督部/消防署/環境部局)へ事前照会しましょう。
すぐ使えるチェックリスト
- 発電機の定格:10 kW超?(12.5 kVA以上)→ 主任技術者&保安規程が必須
- 申請方法:保安ネットで電子申請
- 受電方式:高圧受電(1万V以上)なら工事計画届の要否を確認
- 環境:固定運用・大型消費量ならばい煙発生施設の届出要否を確認(50 L/h/35 L/h目安)
- 配線工事:第一種/第二種+認定従事者の範囲を確認、軽微な工事例外の有無も
- 燃料:合算で1/5基準や指定数量を超えないか。タンク設置は所轄と事前協議
【参考リンク(公式)】
・移動用保安規程モデル(経産省)/手続き案内:リンク
・保安規程の記載事項(施行規則第50条の考え方):リンク
・主任技術者の選任・届出(第43条)案内:リンク
・工事計画届(需要設備・高圧受電):リンク
・ばい煙発生施設の判定目安(50 L/h・35 L/h):リンク
・保安ネット(電子申請)ポータル:リンク / 電子申請が標準:リンク
・電気工事士の従事範囲・軽微な工事:従事範囲/軽微な工事
・消防法 指定数量と1/5基準(例示):リンク
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。
★発電機レンタルなら発電機.jp★
2KVA~1100KVAまで豊富にラインアップ。緊急時やイベントにも迅速対応!
お気軽にご相談ください!
\ 発電機.jpからのおしらせ/
発電機レンタル・購入は 発電機.jp におまかせ!
国内トップクラス 2,800台超 の保有から、
現場にピッタリの機種をスピード手配します。
便利な無料ツールもご用意しています。お気軽にご利用ください!
📩 WEBからのご相談・お見積りはこちら
「どの発電機を選べばよいか分からない」「ケーブルも一緒に手配したい」など、
専任スタッフが用途にあわせてご提案いたします。
※お急ぎの場合も、まずはフォームからご連絡ください。担当者より折り返しご案内いたします。