2025.08.01
電源車とは?(移動式発電機)の届け出・資格・関連法令まとめ 「教えて発電くん!」
最終更新日:2025.08.19
- 教えて発電くん
- 知識
- 法律

電源車(移動式発電機)の届け出・資格・関連法令まとめ
◆ 本記事は 2025 年 8 月 1 日 現在の法令・通達に基づき作成しています。
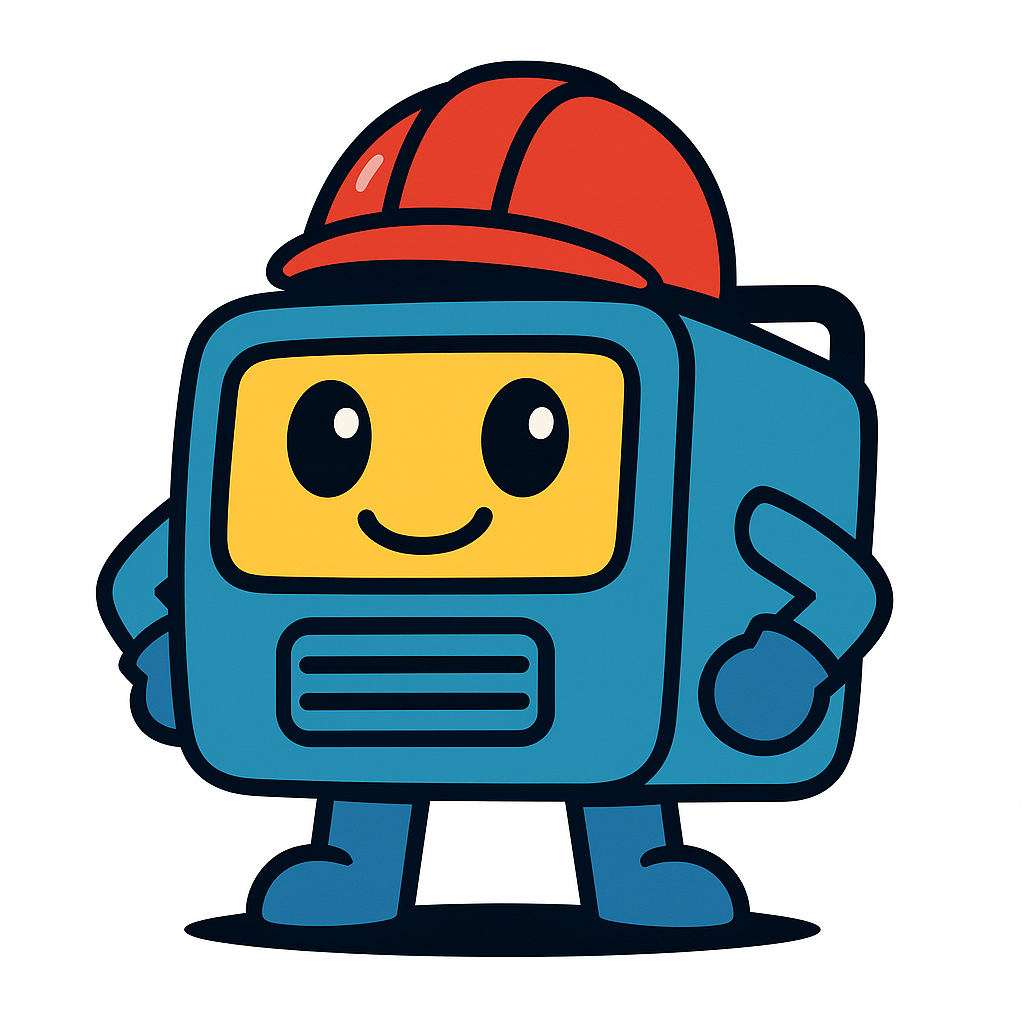
発電くんのワンポイント!
電源車は出力と使用期間で必要な「届け出・資格・法令」が変わるよ。
まずは自分の現場がどの区分に当てはまるかをチェックしよう!
電源車は出力と使用期間で必要な「届け出・資格・法令」が変わるよ。
まずは自分の現場がどの区分に当てはまるかをチェックしよう!
1. 電源車とは?
電源車は、エンジンで発電機を駆動して外部へ電力を供給できる車両型の発電設備。
災害・停電・工事現場・イベント・病院など、商用電源が使えない場所で活躍します。
2. 出力区分ごとの法令・手続き一覧
| 区分 | 主な用途 | 届け出・資格 | 主な法令 |
|---|---|---|---|
| 10 kW 未満 (600V 以下) |
小規模イベント・照明・防災 |
|
電気工事士法/消防法(燃料管理)/騒音規制法 |
| 10 kW 以上 ※使用期間 6 か月超 |
仮設現場・イベント・復旧用 |
|
電気事業法 42・43 条/電気工事士法/消防法/騒音規制法 |
| 10 kW 以上 ※使用期間 6 か月以内 (臨時の運用) |
短期イベント・災害対策・フェス・スポーツ大会 |
|
電気事業法(移動用の運用指針)/消防法/騒音規制法 |
| 高圧設備を含む または 大容量(例:50 kW 超) |
大規模工事・工場・病院 |
|
電気事業法(技術基準等)/電気工事士法/消防法/騒音規制法/建築基準法(長期設置時)/道路交通法(運行時) |
※「6 か月」は法令の明文化ではなく、行政運用上の慣例的目安。同一場所での長期定置は固定扱いとなる場合があります。必ず所轄へ事前相談してください。
発電くんの補足!
10 kW を超える可搬型・電源車は「移動用電気工作物」=自家用電気工作物扱いだよ。
だから保安規程の届出・主任技術者(外部委託等含む)の選任が基本!
使用期間や体制に応じた運用は所轄の判断なので、案件ごとに確認してね。
10 kW を超える可搬型・電源車は「移動用電気工作物」=自家用電気工作物扱いだよ。
だから保安規程の届出・主任技術者(外部委託等含む)の選任が基本!
使用期間や体制に応じた運用は所轄の判断なので、案件ごとに確認してね。
【消防法のポイント】
ガソリン 200 L/軽油 1,000 L を超えると「指定数量以上」扱いで、貯蔵所や取扱所の許可が必要。
1/5(ガソリン 40 L、軽油 200 L)以上~未満は届出が必要になるよ。
3. その他関連法令・手続き
- 消防法:ガソリン 200 L・軽油 1,000 L が規制ライン。指定数量の 1/5 を超えると届出、超えると許可が必要。
- 道路交通法・車両法:公道走行は車検・自賠責等に適合。危険物運搬時は「危」標識(オレンジ板等)の掲示・装備要件を確認。
- 道路使用・道路占用:公道上での停車運用やケーブル布設を伴う場合、道路使用許可(警察)や道路占用許可(道路管理者)が必要となる場合あり。
- 建築基準法・都市計画法:長期定置(目安 6 か月超)では建築物扱い・用途地域等の規制確認が必要。
- 騒音規制法・振動規制法:区域区分・条例により昼間 45–70dB 程度の目安などが設定。自治体の届出基準を確認。
4. よくある現場 Q&A
Q. 50 kW 以下の電源車は主任技術者なしで使える?
A. いいえ。10 kW を超えた時点で保安規程届・主任技術者(外部委託等含む)の体制整備が基本です。
ただし使用期間・運用体制に応じた扱いは所轄判断なので、事前相談が確実です。
A. いいえ。10 kW を超えた時点で保安規程届・主任技術者(外部委託等含む)の体制整備が基本です。
ただし使用期間・運用体制に応じた扱いは所轄判断なので、事前相談が確実です。
Q. 短期イベント(3 日間)で 30 kW の電源車を使う場合の手続きは?
A. 「移動用電気工作物」として保安規程の届出が必要。
主任技術者の扱いや提出方法は所轄の最新案内に従ってください(保安ネットの電子申請に対応・推奨)。
A. 「移動用電気工作物」として保安規程の届出が必要。
主任技術者の扱いや提出方法は所轄の最新案内に従ってください(保安ネットの電子申請に対応・推奨)。
Q. 分電盤や仮設盤への接続は資格が必要?
A. はい。出力にかかわらず第一種または第二種電気工事士(自家用の低圧は認定電気工事従事者の範囲あり)が工事を行う必要があります。
無資格作業は労働安全衛生法/電気工事士法違反となるおそれがあります。
A. はい。出力にかかわらず第一種または第二種電気工事士(自家用の低圧は認定電気工事従事者の範囲あり)が工事を行う必要があります。
無資格作業は労働安全衛生法/電気工事士法違反となるおそれがあります。
Q. 燃料や騒音の管理についての注意点は?
A. 燃料は消防法の数量基準に従って申請・掲示・設備を整えましょう。
騒音は区域区分・条例で基準や届出要否が変わります。早めに自治体へ確認を。
A. 燃料は消防法の数量基準に従って申請・掲示・設備を整えましょう。
騒音は区域区分・条例で基準や届出要否が変わります。早めに自治体へ確認を。
5. まとめ・安全運用のポイント
- 電源車は10 kW 超で「移動用電気工作物」。保安規程届・主任技術者の体制整備が基本。
- 「6 か月」は慣例目安。長期定置は固定扱いとなる場合あり。事前に所轄と調整。
- 提出は保安ネットの電子申請に対応(推奨)。受付方法は所轄の最新案内を確認。
- 配線・設置・接続は有資格者(電気工事士)が実施。
- 消防法・騒音規制・道路使用/占用・車両法など他法令も忘れずに。
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。(最終確認日:2025-08-19)
発電くんからひとこと
法令・手続きは「これで十分かな?」と思ったら、迷わずに相談!
みんなの現場が安全・安心になるよう、最新情報の確認もお忘れなく。
法令・手続きは「これで十分かな?」と思ったら、迷わずに相談!
みんなの現場が安全・安心になるよう、最新情報の確認もお忘れなく。
★発電機レンタルなら発電機.jp★
2KVA~1100KVAまで豊富にラインアップ。緊急時やイベントにも迅速対応!
お気軽にご相談ください!
\ 発電機.jpからのおしらせ/
発電機レンタル・購入は 発電機.jp におまかせ!
国内トップクラス 2,800台超 の保有から、
現場にピッタリの機種をスピード手配します。
便利な無料ツールもご用意しています。お気軽にご利用ください!
📩 WEBからのご相談・お見積りはこちら
「どの発電機を選べばよいか分からない」「ケーブルも一緒に手配したい」など、専任スタッフが用途にあわせてご提案いたします。
※お急ぎの場合も、まずはフォームからご連絡ください。担当者より折り返しご案内いたします。