ケーブルの絶縁抵抗ってなに? 教えて発電くん!
- 教えて発電くん
- 知識
- 法律
- 故障・修理

教えて発電くん!ケーブルの絶縁抵抗ってなに?
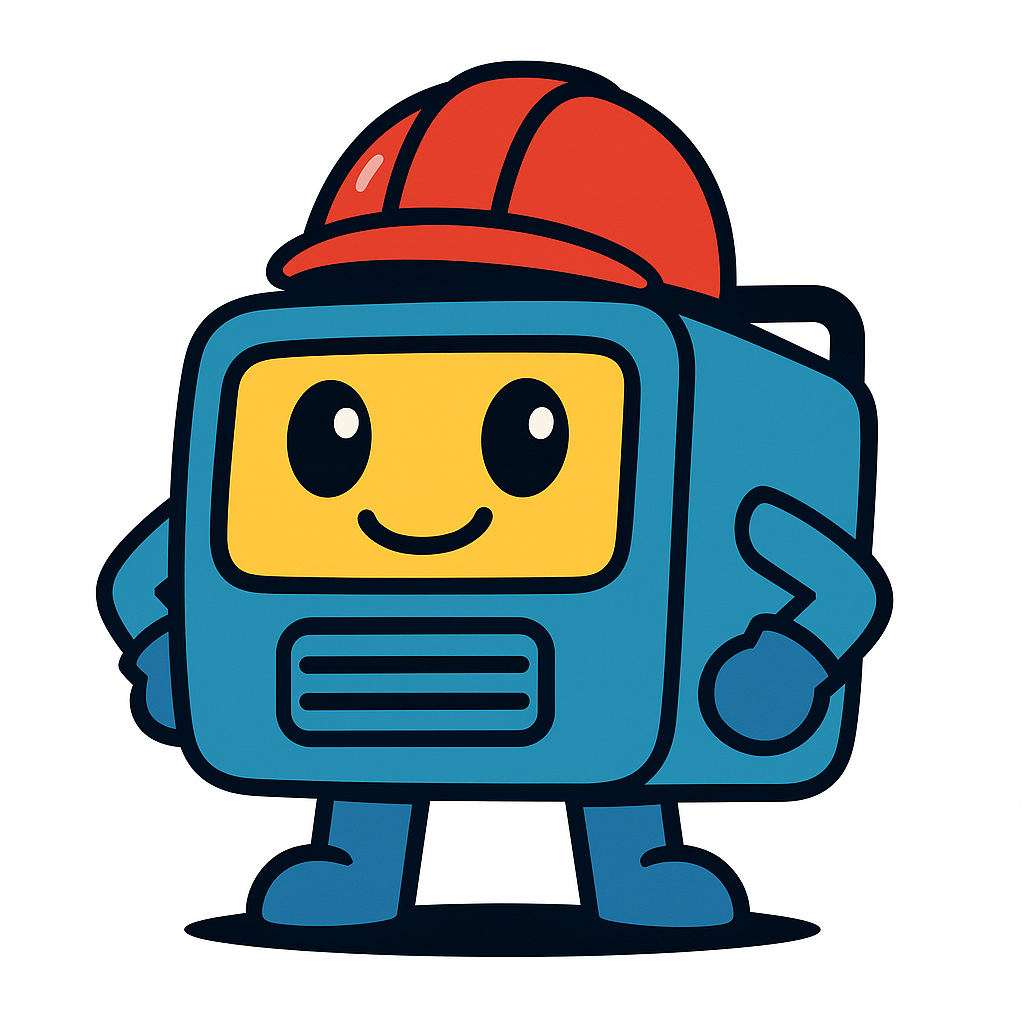
こんにちは、発電くんです!
今日は現場でもよく質問される「ケーブルの絶縁抵抗」について、押さえるべきポイントを分かりやすく解説します。
■ ケーブルの絶縁抵抗とは?
絶縁抵抗とは、ケーブルの導体と外部(大地や他の導体など)との間の“電気を通しにくさ”を示す値です。
この数値が高いほど、ケーブルの絶縁性能が保たれており、漏電や感電のリスクが低くなります。
逆に、絶縁抵抗が低下すると漏電・感電・発熱・発火などの重大事故につながる可能性があります。
だからこそ、「使う前の確認」+「定期点検」がとても大切です。
■ 新品ケーブルの絶縁抵抗値の目安(JIS/仕様表のイメージ)
新品ケーブルの絶縁抵抗は、ケーブルの種類や断面積に加え、長さや温度の影響も受けます。
ここでは現場でよく使う代表例として、カタログ等に掲載されることが多い「最小絶縁抵抗(20℃・MΩ・km)」の目安をまとめます。
| ケーブル種類 | 最小絶縁抵抗(20℃・MΩ・km) | 備考 |
|---|---|---|
| IV/HIV | 50以上(小断面)/40以上(太径) | サイズにより規格値が異なる |
| 600Vキャブタイヤ(VCT) | 30~50 | 断面積により変動 |
| 600V CV(架橋PE) | 900~2,500 | 断面積により変動(※IVと別枠で扱う) |
| 計装/制御(例:CVV) | 50以上(仕様により上回る場合あり) | 材質・構造で変動 |
*短尺(1~3m程度)では、メガーの実測値(MΩ)が大きく出やすく、カタログの「MΩ・km」と単位が揃いません。
そのため、カタログやJISの「最小絶縁抵抗(MΩ・km)」と比較したい場合は、測定値を20℃・1km値(MΩ・km)に換算して評価します。
換算式:R20(MΩ・km) = Rt(MΩ) × Kt × (L/1000)
(⇔ Rt = R20 × 1000 / (Kt × L))
※ L はケーブル長(m)、Kt は温度換算係数です。
なお、温度が上がると絶縁抵抗は低下するため、評価は JIS C 3005 の温度換算係数(Kt)で20℃に換算して行いましょう。
■ 法令で定められた最低絶縁抵抗値(低圧回路)
「電気設備に関する技術基準を定める省令」第58条では、使用電圧ごとに最低限満たすべき絶縁抵抗値が定められています。
これはあくまで最低ラインです。実務では、後述の管理目安のように、より高い値を基準にして安全率を確保することをおすすめします。
| 使用電圧 | 対地電圧 | 最低絶縁抵抗値 | 主な例 |
|---|---|---|---|
| 300V以下 | 150V以下 | 0.1MΩ | 単相100V回路など |
| 300V以下 | 150V超 | 0.2MΩ | 単相200V/三相200V回路 |
| 300V超 | ―(区分なし) | 0.4MΩ | 三相400V系など |
※ 上表の最低絶縁抵抗値は電路(回路)としての絶縁抵抗(MΩ)の下限です。原則としてメガーの実測値(MΩ)で判定します。
※ 絶縁抵抗の測定が困難な場合は、使用電圧が加わった状態での漏えい電流が1mA以下であることにより判定できる扱いがあります(技術基準の解釈)。
※ 上表の基準はケーブルの長さを問わず適用されます。たとえば長さ3m以下の短尺ケーブルでも、 0.1MΩ/0.2MΩ/0.4MΩの基準を下回らないか確認してください。
(管理目安)絶縁抵抗値が3MΩを下回る場合は要注意。1MΩ以下は危険レベル。
※ 「3MΩ注意/1MΩ危険」は社内の管理目安であり、法令の最低値ではありません。用途・仕様によっては別基準(例:500V印加で5MΩ以上等)が適用される場合があります。
■ 絶縁抵抗値が低くなる原因は?
絶縁抵抗が低下する原因は主に次のとおりです。
- 経年劣化
- 傷や断線、圧迫などの物理的ダメージ
- 湿気や水分の浸入
- 絶縁体表面の汚れや粉じんの付着
見た目が大丈夫そうでも、内部に水分が回っていたり、押しつぶしで絶縁が薄くなっていたりすることもあります。
そのため、外観確認+測定のセットで確認するのが安心です。
■ 絶縁抵抗値の測定方法
絶縁抵抗計(メガー)を使用して測定します。測定の基本は次のとおりです。
- 原則:必ず電源を切り、発電機・分電盤・負荷機器を含めて安全を確保してから測定する
- 測定箇所:主に「導体-地間」「導体-導体間」など
- 低圧電路では500Vレンジを用いることが多い(機器の定格・回路構成により100V/250V等を選ぶこともある)
※ サージ保護素子や電子機器が接続されたまま高い試験電圧をかけると、誤動作・故障の原因になる場合があります。現場の手順書・機器仕様に沿って実施してください。
■ 現場レポート:絶縁抵抗値が低かったらどうする?
ある現場で600Vキャブタイヤケーブルの絶縁抵抗を測定したところ、2MΩしかありませんでした。
外観を確認すると、地面との接触部に傷があり、水分と泥汚れも付着していました。
乾燥させても数値が戻りにくかったため、事故予防の観点から新品ケーブルへ交換しました。
(管理目安)3MΩを下回る場合は要注意。1MΩ以下は危険レベル。
■ 絶縁抵抗値の管理ポイントまとめ
- 新品ケーブルは種類ごとの仕様(MΩ・km)と法令最低値(MΩ)をそれぞれ確認する
- 点検では、外観(傷・つぶれ・水分・汚れ)と測定結果をセットで判断する
- 数値が低い場合は、まず乾燥・清掃・端末処理の見直しを行い、改善しなければ交換を検討する
- 湿気・水濡れが多い現場は、保管方法(防水・通気・端末保護)も含めて対策する
■ よくある質問
- Q. 新品でも絶縁抵抗が低い場合は?
- A. 保管時の湿気などで一時的に低下していることがあります。 乾燥・清掃・端末処理の見直しで回復する場合もありますが、改善しない場合は交換を検討してください。
- Q. 絶縁抵抗の測定頻度は?
- A. 年1回以上の点検が目安ですが、屋外・水濡れ・粉じんが多いなど過酷な現場では、より高頻度の点検が安心です。
■ まとめ
ケーブルの絶縁抵抗管理は、事故防止や安全な電気使用の基本です。
法令が定める最低絶縁抵抗値(MΩ)と、カタログ・規格の最小絶縁抵抗(MΩ・km)は、評価の「ものさし」が違います。
それぞれの意味を押さえたうえで、余裕を持った管理目安(3MΩ以上など)を設定し、定期点検と早めの対応を心がけましょう。