発電機によく使われる用語集(2025年版)教えて発電くん!
- 教えて発電くん
- 知識
 【教えて発電くん!】発電機によく使われる用語集(2025年版)
【教えて発電くん!】発電機によく使われる用語集(2025年版)
発電機を選定・運用する際には、専門用語が多く登場します。本コラムでは、建設現場・イベント・災害対策でよく使われる発電機関連用語をわかりやすく解説します。初めて発電機に触れる方から専門業者の方まで、辞書としてご活用ください。
※本コラムの内容は2025年11月時点の法令・各種資料をもとに作成しています。
🔌 基本の電気用語
■ 電圧(V:ボルト)
電気を押し出す力の大きさ。一般的な単相100V・200V、三相200V・400Vなどがある。
■ 電流(A:アンペア)
電気の流れる量。電圧と電流の積が電力となる。
■ 周波数(Hz)
電気の振動数。日本では地域により50Hz(東日本)と60Hz(西日本)に分かれる。
■ 電力(kW)
電気の仕事量。発電機の出力選定で最重要となる指標。
⚙️ 発電機に関する用語
■ 定格出力(kVA/kW)
連続運転が可能な出力量。
kVA(皮相電力)とkW(有効電力)があり、計算時は力率0.8が一般的。
■ 力率(PF:Power Factor)
電力の利用効率。一般的には0.8で計算される。
計算式:kVA × 0.8 = kW
■ 三相・単相
- 単相:一般家庭や小型機器で使用(100V/200V)
- 三相:モーター・溶接機・建設機械に多い(200V/400V)
■ 始動方式(セル・リコイル)
- セルスタート:キーまたはボタンで始動
- リコイル:手動でロープを引いて始動
■ 同期運転(並列運転)
複数の発電機を同期(電圧・周波数・位相・相順を合わせて)させ、同一の母線に並列接続して出力を増やす運転方式。
容量を柔軟に調整できる一方で、同期条件の管理や故障時の影響範囲など、設計・施工・運用には専門知識が必要となる。
■ サイマル発電機/同時出力
メーカーが「サイマル」「同時出力」などと呼ぶ機能・シリーズの総称。
- 三相200Vと単相100V・200Vを同時に取り出せる機能
- 専用ケーブルで2台の発電機を接続し、出力を合算して使用できる機能(並列運転に近い運用)
仕様はメーカー・機種ごとに異なり、「どの電圧を」「どの容量まで」同時使用できるかは必ず仕様書・取扱説明書で確認すること。技術用語としての「同期運転(並列運転)」と完全に同じ意味ではない点に注意。
■ AVR(自動電圧調整装置)
電圧を安定させる機能。精密機器の保護に重要。
■ インバーター発電機
出力を電子的に整え、波形が安定した発電機。静音性・燃費に優れるが、大出力はやや苦手。
🔧 現場でよく使う専門用語
■ 始動バッテリー
セルスタート式発電機のエンジン始動に必要なバッテリー。
■ 連続運転時間
燃料満タンで運転できる時間。実運用では負荷によって短くなる点に注意。
■ 端子台(R相・S相・T相・U/V/W)
三相接続で使われる端子名称。誤接続によるトラブルが多いため要注意。
■ キャブタイヤケーブル(CV・VCTなど)
発電機と機器を接続する耐久ケーブル。太さ・長さ・許容電流の選定が必須。
■ 電圧降下
ケーブルが長いほど発生する電圧の低下。モーター類のトラブル原因となる。
📦 燃料・保守用語
■ 軽油(A重油・ガソリン・LPガス)
発電機の燃料区分。多くの可搬型発電機は軽油を使用するが、機種によってはA重油・ガソリン・LPガス仕様もある。
■ オイル警報・停止
エンジンオイル量が不足すると自動停止する保護機能。
■ メーカー点検(法定点検)
非常用発電機は建築基準法・消防法で点検が義務付けられている。
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。
⚡ 電気品質・保護装置の用語
■ THD(総合高調波ひずみ率)
インバーター負荷や電源装置が発生させる高調波成分の割合を示す指標。値が大きいほど波形が歪み、機器トラブルや発熱の原因となる。
■ 高調波
正弦波(基本波)に重なって流れる周波数の高い成分。変換装置・インバーター・LED照明などで発生しやすく、発電機の過熱やブレーカーの誤動作を招く場合がある。
■ NFB(ノーヒューズブレーカー)
過電流が流れたときに自動で回路を遮断する配線用遮断器。ヒューズ交換が不要で、発電機の保護にも使われる。
■ 漏電遮断器(ELB/漏電ブレーカー)
電路から大地へ電流が漏れたときに検知して遮断する装置。感電・火災防止のため、屋外現場や仮設配電盤では特に重要。
■ 接地(アース)
機器の金属部分を大地と電気的につなぎ、異常電圧から人や機器を守る仕組み。接地抵抗値の管理が安全上のポイント。
🧷 配線・相に関する用語
■ 単相2線式・単相3線式
- 単相2線式:100V専用など、線が2本の方式。
- 単相3線式:100Vと200Vを同時に取り出せる方式。分電のバランスが重要。
■ 中性線(N相/N線)
単相3線式や三相4線式で、電圧の基準となる線(ニュートラル)。図面や端子表示では「N」と表記される。
■ O相
三相4線式などで「4本目の線」を示すために、図面や端子表で慣習的に使われることがある表記。
- 中性線(N線)をO相と表記している場合もあれば、単なる相線として扱っている場合もある。
- 規格上の正式名称ではないため、「O相=中性線」と決めつけないことが重要。
- 実際の役割(中性線なのか、相線なのか)は、必ず結線図・仕様書・盤の銘板表示で確認する。
■ 相順
三相電源の相がつながる順番。モーターの回転方向に関わるため、発電機接続時には相順チェッカー等で確認する。
▶️ 発電機の種類・運転形態に関する用語
■ 可搬型発電機(移動式発電機)
トラックやフォークリフトなどで現場へ運び、屋外や仮設設備で使用するタイプの発電機。建設現場・イベント会場・災害対策拠点などで広く使われ、レンタル機としての利用も多い。
- 仮設用途が中心で、必要な場所へ持ち込んで使用する。
- ビルに据え付ける非常用自家発電設備とは、設置場所・法令上の扱い・保守点検の考え方が異なる。
- 同じ「非常時の電源」として使っていても、建築基準法上の「自家発電設備」に該当しないケースが多い点に注意。
■ 常用発電機
普段から電源として継続的に使用する発電機。工場・事業場・プラント設備の常用電源として用いられることが多く、連続運転時間・燃費・保守性が重要視される。
可搬型発電機を「常用用途」で使うケースもあるが、長時間運転・高負荷運転が前提となる場合は、仕様やメンテナンス条件を必ず確認することが望ましい。
■ 非常用発電機(自家発電設備)
停電時など、非常時のみ運転することを前提とした発電機設備。建築基準法および消防法上の「自家発電設備」「非常電源」として扱われる場合がある。
おもにビル・病院・庁舎・工場などの建築物に据え付けで設置され、非常用照明・非常用エレベーター・排煙設備・スプリンクラー設備など、避難や安全に関わる設備への電源を担う。
参考リンク:
・建築基準法施行令(e-Gov)
・消防法施行令(e-Gov)
・消防法施行規則(e-Gov)
⚠️ 法令・通達は改正される場合があります。最新情報は必ず所轄官庁の公表資料をご確認ください。
■ 自動切替盤(ATS/AMF盤)
商用電源の停電を検知し、発電機を自動起動して電源を切り替える盤。復電時には商用電源へ自動復帰する。
■ 無停電電源装置(UPS)
停電時にバッテリーで瞬時に電力を供給する装置。発電機と組み合わせて、サーバーや制御装置など「瞬断できない負荷」を保護する。
📊 負荷・運転指標に関する用語
■ 始動電流(突入電流)
モーターやコンプレッサーが起動するときに、一時的に定格電流の数倍流れる現象。発電機容量選定の重要ポイント。
■ 負荷率
発電機の定格出力に対して、実際にどれくらいの負荷をかけているかを示す割合(%)。負荷率が低すぎても高すぎてもトラブルの原因となる。
■ 実効値(RMS)
交流電圧・電流の有効な大きさを示す値。計測器や仕様書に記載される電圧・電流は、基本的にこの実効値を指す。
🎤 現場レポート:発電くんのひとこと
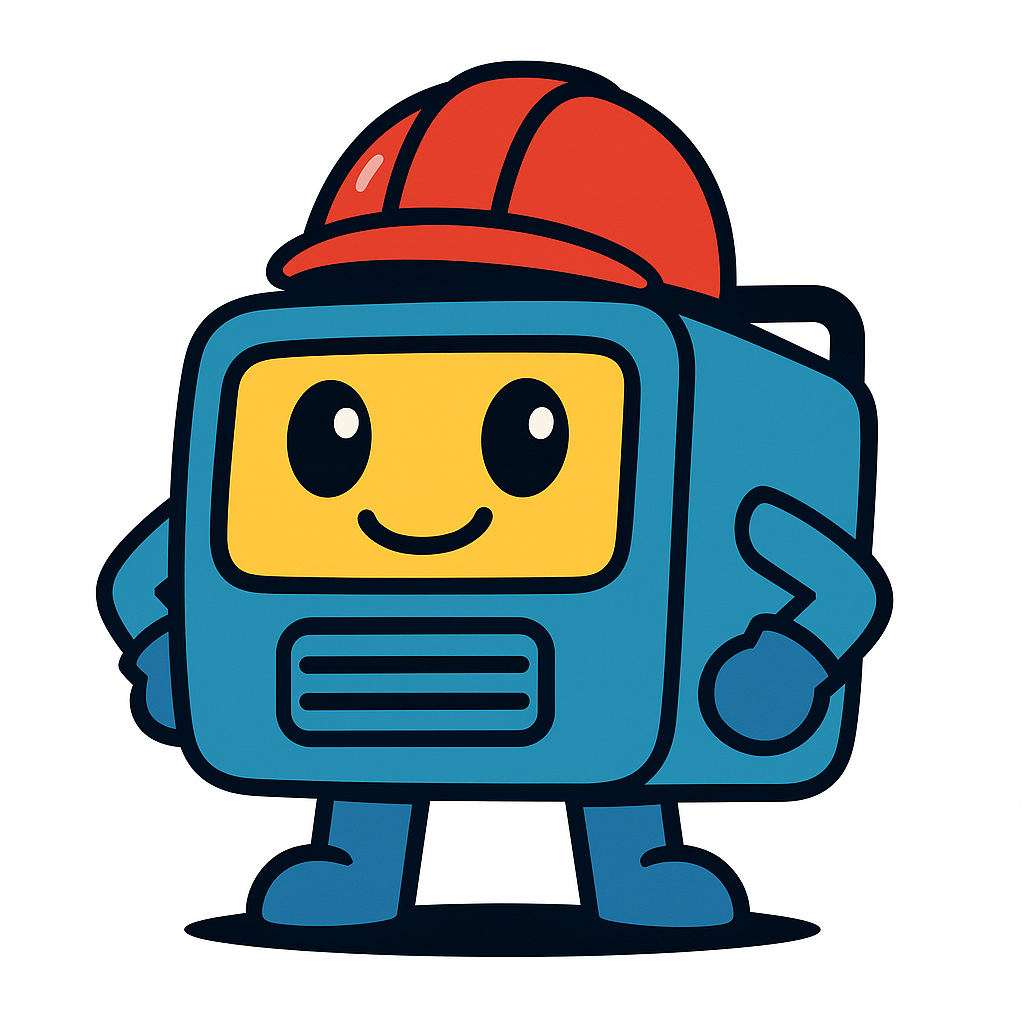
発電くん:
「用語を正しく理解しておくと、現場でのトラブルを大幅に減らせるよ!特に“力率”“始動電流”“相順”“接地”あたりは、発電機の選定と安全に直結するポイントなんだ。」
\ 発電機.jpからのおしらせ/
発電機レンタル・購入は 発電機.jp におまかせ!
国内トップクラス 2,800台超 の保有から、
現場にピッタリの機種をスピード手配します。
便利な無料ツールもご用意しています。お気軽にご利用ください!
📩 WEBからのご相談・お見積りはこちら
「どの発電機を選べばよいか分からない」「ケーブルも一緒に手配したい」など、
専任スタッフが用途にあわせてご提案いたします。
※お急ぎの場合も、まずはフォームからご連絡ください。担当者より折り返しご案内いたします。